EDVとは?株価や配当利回りはどれくらいなのか?EDVのメリット・デメリットや配当金生活について初心者向けにわかりやすく解説します!
EDVとは
EDV(正式名称:バンガード・超長期米国債ETF)は、「ブルームバーグ・バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックス」という指数に連動するインデックス型の債券ETFです。
ETFとは上場投資信託と呼ばれる投資信託の一種で、証券取引所で取引される投資信託となっています。
ETFの特徴としては、投資信託に比べて手数料が低い傾向にあることや、リアルタイムでの注文が出来るといった点が挙げられます。
インデックス型のETFとは、株価指数の動きに連動した運用成果を目指すETFであることを意味します。
ETFについて詳しく知りたい方は以下の記事をどうぞ!
EDVは、ETFの中でも債券を対象とした指数に連動する債券ETFとなっています。
ブルームバーグ・バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックスとは
ブルームバーグ・バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックスは、残存期間が20~30年の米国財務省証券ストリップス債で構成される指数です。
この指数の特徴は、米国債の中でも残存期間が20~30年の超長期国債で構成されていることにあります。
超長期国債の特徴としては、ボラリティ(価格変動の度合い)やリターンが短期国債と比較して高いことなどが挙げられます。
ストリップ債とは
ストリップ債とは、利付債の元本部分とクーポン(利息)部分が分離され、それぞれの部分がゼロクーポン(無利息)の割引債として販売される債券のことです。
ストリップ債を理解しやすいように、債券の種類を以下でまとめました。
| 利付債 | 債券の保有者に利息が支払われる債券。満期になると額面金額で買い取ってもらえる。 |
| 割引債 | 利付債に比べて利息が少ない代わりに、額面金額よりも低い価格で購入することが出来る債券。満期になると額面金額で買い取ってもらえる。 |
| ゼロクーポン債 | 利息の支払いがない代わりに、額面金額よりも低い価格で購入することが出来る債券。満期になると額面金額で買い取ってもらえる。割引債の一種。 |
| ストリップ債 | ゼロクーポン債の中でも、債券の元本部分と利息部分を別にして、それぞれをゼロクーポン債として購入することが出来る債券。満期になると額面金額で買い取ってもらえる。 |
EDVの株価

アメリカの大手情報サービス会社であるBloombergによると、2024年6月7日時点でのEDVの株価は75.04米ドル(日本円で約1万1,735円)となっています。
※三井住友銀行のリアルタイム為替レート(2024年6月7日 午後0時35分 現在)を使用しました。
EDVの配当利回り
Bloombergによると、2024年6月7日時点でのEDVの分配金利回りは4.10%となっています。
これは、債券ETFとしてはかなり高い利回りであると言えます。
EDVで配当金生活シミュレーション
続いて、EDVで配当金生活をする場合のシミュレーションを行います。
このシミュレーションでのEDVの分配金利回りを4.10%と想定して、投資金額による年間の分配金金額を算出します(ただし税金を考慮せず、税引前の金額とする)。
シミュレーションの結果は以下の通りです。
| 投資金額 | 年間の分配金金額 |
| 100万円 | 4万1,000円 |
| 500万円 | 20万5,000円 |
| 1,000万円 | 41万円 |
| 1,500万円 | 61万5,000円 |
| 2,000万円 | 82万円 |
| 2,500万円 | 102万5,000円 |
| 3,000万円 | 123万円 |
| 3,500万円 | 143万5,000円 |
| 4,000万円 | 164万円 |
| 5,000万円 | 205万円 |
| 6,000万円 | 246万円 |
| 7,000万円 | 287万円 |
| 8,000万円 | 328万円 |
| 9,000万円 | 369万円 |
| 1億円 | 410万円 |
EDVのメリット

手数料(コスト)が低い
EDVのメリットとして、手数料の低さが挙げられます。
ETFを保有する場合、保有している期間に経費(手数料)を支払う必要があります。
Bloombergによると、2024年6月7日時点のEDVの経費率は価格の0.06%となっており、これは他の海外ETFと比較して低い水準にあると言えます。
以下で、2024年6月7日時点での海外ETFの経費率の例を挙げてみました(Bloomberg参照)。
| ETF | 経費率 |
| QYLD | 0.61% |
| PFF | 0.46% |
| SPYD | 0.07% |
| BND | 0.03% |
| JEPI | 0.35% |
| HDV | 0.08% |
| VTI | 0.03% |
| VIG | 0.06% |
| QQQ | 0.20% |
このように、EDVの経費率は他の海外ETFと比較しても低い水準にあることが分かります。
ETFを長期的に運用していく上で、経費率はリターンに大きな影響を及ぼす要因となるため、経費率の低さは大きなメリットとなります。
EDVと同水準で経費率が低い他の海外ETFについて詳しく知りたい方は以下の記事をどうぞ!
リスクが低い
EDVは米国の超長期国債を対象としたETFとなっていますが、国債は一般的に金融資産の中でトップクラスにリスクが低いとされています。
その理由としては、国債の発行体が国であるからです。
国が破綻するリスクは一般企業と比較してはるかに低いと考えられます。そのため、一般企業が発行する株式や債券に比べて、途中で国債を換金出来なってしまう可能性がとても低いのです。
このことから、EDVは株式のみで構成されたETFと比較するとリスクが低いと考えることが出来ます。
デフレ時に価格が上昇する
一般的に、株式と債券の価格は逆の動きをすると言われています。
株式の価格(株価)は、インフレ時に上昇し、デフレ時に下落します。
ところが債券の価格は、インフレ時に下落し、デフレ時に上昇します。
この理由としては、市場金利の動きが関係しています。以下がその仕組みを説明したものになります。
| インフレ時 | 景気が上昇を迎える→過度に上昇した景気を抑制しようとする→お金の動きを抑制するために金利を引き上げる(金融引き締め)→新たに発行される債券の方が利回りが高くなるため、現在保有している債券の価格が下落する |
| デフレ時 | 景気が下落を迎える→過度に下落した景気を活発化させようとする→お金の動きを促進するために金利を引き下げる(金融緩和)→新たに発行される債券の方が利回りが低くなるため、現在保有している債券の価格が上昇する |
このため、仮に米国株と同時に米国債を保有していた場合、米国のデフレ時に保有する米国株の価格が下落したときに米国債の価格は上昇するため、資産の減りを小さくすることが出来ます。
債券ETFとしては配当利回りが高い
先述した通り、国債は株式などと比較してリスクが低い金融資産と考えることが出来ます。
しかし、その一方で国債の利回りは株式の配当利回りよりも低い場合が多いです。
ですがEDVは、株式で構成されるETFと比較しても遜色ない水準の高い分配金利回りを誇っています。
以下で、他の海外ETFの分配金利回りの例を紹介しておきます(2024年6月7日時点)(Bloombergで算出された数値を使用しています)。
| ETF | 分配金利回り |
| QYLD | 11.02% |
| PFF | 6.17% |
| SPYD | 3.68% |
| BND | 3.63% |
| JEPI | 7.64% |
| HDV | 3.05% |
| VTI | 1.38% |
| VIG | 1.70% |
| QQQ | 0.50% |
このように、EDVは一般的に株式よりもリスクが低いとされる国債に投資するETFでありながらも、分配金利回りでは株式に投資するETFに匹敵するほどの高さとなっています。
EDVよりも分配金利回りが高い海外ETFについて詳しく知りたい方は以下の記事をどうぞ!
EDVのデメリット

ボラリティが高い
ボラリティとは、価格変動の度合いの大きさのことです。
価格変動の度合いが大きい場合、ボラリティが大きいと表現します。反対に、価格変動の度合いが小さい場合は、ボラリティが小さいと表現します。
EDVが投資対象とするような国債は、ボラリティがとても大きいです。
なぜなら、EDVに含まれる国債は残存期間が20~30年の超長期国債であり、満期まで保有する期間がとても長いため、その分景気の動きの影響を大きく受けるからです。
ボラリティが高いと、デフレ時に価格が上がりやすくなる反面、インフレ時に価格が下がりやすくなってしまうというデメリットがあります。
為替リスクがある
為替リスクとは、為替相場の変動によって外貨建て資産の円換算時の価値が上下するリスクを指します。
為替相場が円安に進行すると、外貨建て資産の円換算時の価値は上昇します。
反対に、為替相場が円高に進行すると外貨建て資産の円換算時の価値は下落します。
そのため、もし円高時に外貨建て資産を円に交換してしまうと損失を出してしまう可能性があります。
円以外の通貨で取引される資産に投資をする場合は為替リスクが伴うため、注意が必要です。
まとめ
EDVは、ボラリティが高いことや為替リスクがあることが懸念点とはなりますが、リターンが比較的大きくリスクも低いETFとなっているため、投資対象としては良い金融資産であると考えることが出来ます。
EDVのおすすめの活用方法としては、以下が挙げられます。
株式や株式を対象としたETFと組み合わせることで、インフレ・デフレの影響による資産価格の変動の幅を抑える。


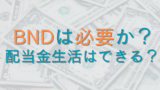






コメント